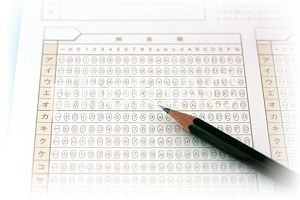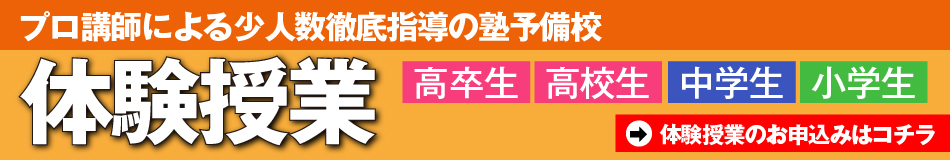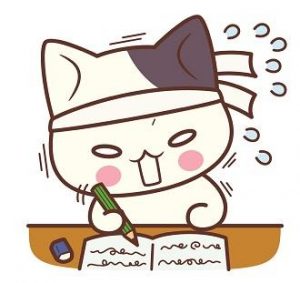こんにちは!茨木本校のPです。
最近はめっきり寒くなってきましたね。
Pはまだ半袖短パン姿で寝ていますが、
もうそろそろ限界を迎えそうです。
さて今回は、
10月末にアップした記事の続きで
暗記のコツ
についてお伝えします。
長い記事になりますが
お付き合いください。
前回の記事では、
暗記に一番必要なことは
回数を重ねること
というふうにお伝えしました。
今回はその回数を減らすには
どうすればいいのかということについて
お話します。
回数を減らすコツ。
それはズバリ、
いろいろな角度で見る
です!
どういうことか
例を使って説明していきますね。
今あなたが赤いリンゴを手にして、
それを口にしたとします。
少し酸味のある味。
あなたは
「あー、リンゴを食べているな」
と感じるはずです。
1週間後
突然、誰かに
「先週あなたは何の果物を食べたか覚えてますか?」
と聞かれたとします。
さて、食べてから1週間経っても
あなたはリンゴを食べたということを
思い出せるでしょうか?
もちろん、思い出せる人は
何人もいると思います。
ただ、思い出せる人は
「リンゴを食べた」
という事実だけを覚えているのではなく、
手に取ったときの重さや
色、味、食感など、
残っている様々な印象のうち
どれかをきっかけにして
思い出しているはずです。
そうです、きっかけが多ければ多いほど
思い出しやすくなるのです。
英単語なども同じです。
unforgettable=「忘れられない」
と、英語と日本語の1対1だけでは
覚えづらいですが、
un(反対) forget(忘れる) able(できる)
と分解してみたり
I had an unforgettable experience.
「忘れられない経験をした。」
など例文やコロケーションを使ったり
いろいろな角度でその単語を見てみると
意味を思い出すきっかけが増えて
何回も何回も覚えなくても
少ない回数で覚えられます。
英単語に限らず
覚えにくいものを
あらゆる角度から眺めてみると
印象に残って覚えやすくなります。
覚えるのが苦手やなーと思ってる人は
ぜひ
いろいろな角度から見てみる
ということを意識してみてください。
以上、長くなりましたが
これにて暗記のコツは一旦終了です。
他にも暗記のコツはいくつかあるので
またの機会にお伝えしますね。
次回は11月末に
やる気スイッチ
というテーマでお届けする予定です。
ではまた!