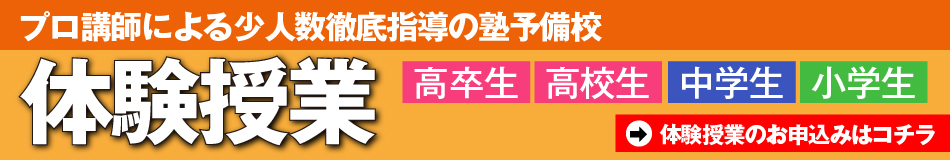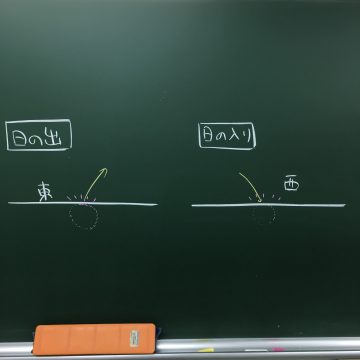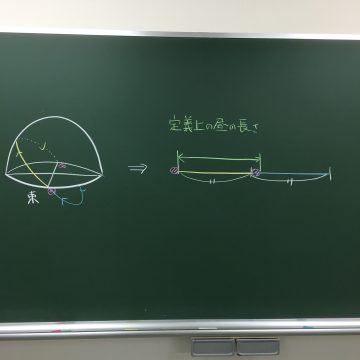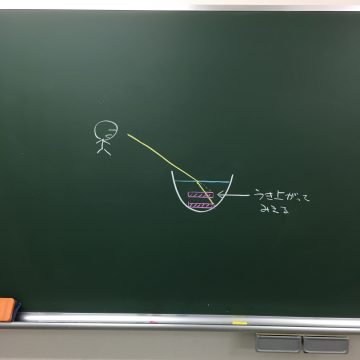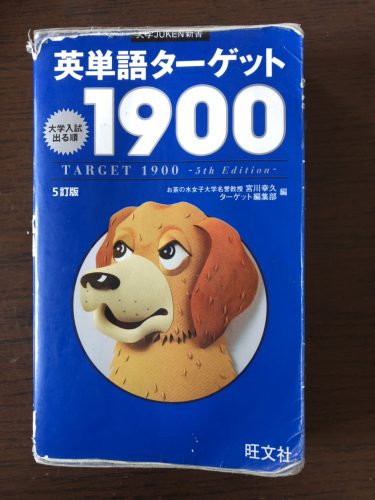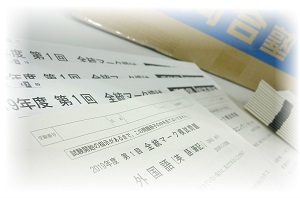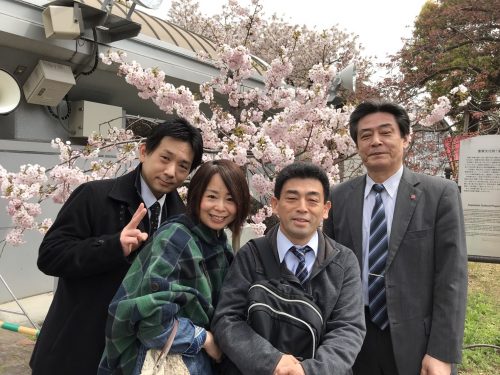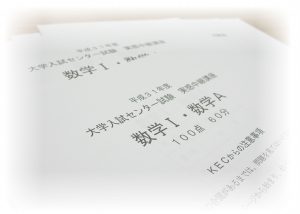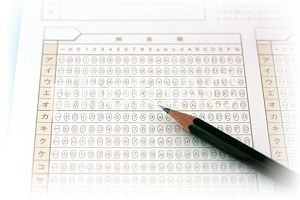こんにちは。茨木本校2230です。
大学入試は秋の推薦入試真只中。
今後はセンター試験,私大前期・中期,
国公立大前期,,,と2月3月まで続きます。
受験プランはもちろん,受験生にもいくつかのタイプが。
ここでは,私大国公立大といった枠組みではなく,
入試時期と○×の組み合わせで考えてみます。
■秋で完結!優等生組
指定校ですーっと進学先が決まった人や,
推薦入試で本命1本釣りって人です。
指定校を取ることができるためには,日頃の行い,
つまりは高校での成績を上位キープできたということ。
真面目に取り組んだ甲斐ありましたね。
進学先でもコツコツと日々努力を忘れないでください。

■秋は安全校確保!ステップアップ狙い組
推薦入試では妥当校をしっかりと抑えることができ,
2月入試へは憧れの大学に絞って調整できますね。
上り調子の勢いよろしく,明るい気分で乗り切れそう。
■秋で凹んだ!リベンジ組第1班
憧れ本命に挑戦したけれど,想定内✕だった人。
あわよくば,といった期待をしすぎていないといえど,
ああやっぱり,,,はショックです。
今の自分に何が足りていませんか。
次回も同じ取り組み方ではイケマセン。
詰めの甘さを噛みしめつつ,2ヶ月後まで自力を蓄えましょう。

■秋で凹んだ!リベンジ組第2班
きっといけてる,だってあの子より私の方が高校ランク上やし,,
なんて気楽に構えてたら逆にアタシが不合格,って人。
大学入試は出身校に関係ないのよ実力つけな,
って再三申し上げた台詞が今頃身に凍む寒空ですね。
クヨクヨなんてしてられません。同じKEC生が合格してるなら,
同じノウハウを身につけたはずの自分ができないはずない。
練習量を増やし,取り組み方を改善して,リベンジを果たそう。
■秋とは無縁!私の番は年明けから組
合否の報告を小耳に,俺には関係ねえって人。
センター試験や私大前期こそが前哨戦となります。
受験回数が少なめな人も多いでしょうが,
いきなり本命を迎えず,まずは練習がてら安全校を1発かまして
入試本番の雰囲気を経験しておくことをお勧めします。
■番外編!おいお過去問これからってのんびり組
夏開けからは毎週過去演習だよ,,,を無視した人。
まだ実力が,,?いつまでも待てません。試験日は迫ってます。
過去問やれば,自分の弱点がわかる。受験すべきかわかる。
もう逃げてられません。今月中に3セット実行すること。
大学受験は長期戦に。
その時々での調子も異なるでしょうし,過去問の出来具合が
そのまま合否に結びつくとは限りません。
上手くいけばラッキー,ダメでもあっさり次のプランへ進めるよう
いくつかの選択肢を前もって考慮しておくことをお勧めします。
あとになって悩むのは,士気に影響を与えますよ。
「もしもプラン」の相談はKEC事務局まで。