こんにちは。茨木本校2230です。
この土日,自習室は大入りに。

定期試験が近くなり,
勉強環境を求めて中高生が積極利用中。
中学生には「定期テスト学習計画表」を準備,
▶目標点
▶本日の取り組み
▶本日の満足度
を記入するシートなのです。
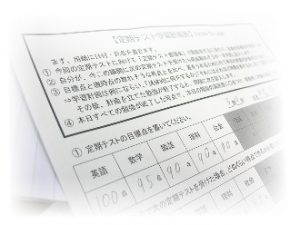
50分机に向かって10分休憩,のセット。
あの子頑張ってるし,私もと,
共に励む姿がいいですね。
休憩時のお菓子タイムもお楽しみ。
6月には「KEC能力診断テスト」を実施。
こちらに向けても毎日の学習を大切に。
こんにちは。茨木本校2230です。
昨日は「第1回全統マーク模試」でした。
日常的なミニテストは,日々の学習深度の判断に有効です。
2230がテストを作るとき,
クラスレベルにあっているか,
時期相応の知識を確認できるか,
正しく運用できているか,
解く速度は適切か,
といったことを考えて作成します。
では,模試は。
マーク模試の出題レベルは,センター試験と同等です。
高3の5月でセンターレベルって,早いです?
数学は高2までの学習範囲からしか出ません。
でも,解けない。間に合わない。
いいんです。
解けなくっても,間に合わなくっても。
今は。
むしろ。
今気ついてほしいことは,
「このまんまだとマズイ」ってことです。
「あぁ,オレってヤバイやん(良くない意味で)」
と後悔するのは誰でもですが,
次の行動ができれば「さすが受験生」です。
それは。
反省としての「できない理由」とその「対策」です。
「まだ習っていない」なら,
教科書で予習したりネットで調べたりできます。
今後覚悟を決めて臨むことができるでしょう。
「知っているけどできなかった」のなら,
時間をかければできるのか。
それでもできないなら理解が甘いのでは。
適切な作業法を振り返ってみましょう。
「できたはずなのに」なら,
ミスした理由を考えましょう。
単なる計算ミスか,手法が下手なのか。
プロの技を盗むべく授業に臨みましょう。

勉強は,がむしゃらに突っ走るだけではありません。
歩み方にも工夫が必要なのです。
時には立ち止まって立ち位置を確認,ですね。
こんにちは。KEC高槻本校の数学・理科担当の川渕です。
いよいよGW。
学生の皆さんは,5月3日から連休,という方がほとんどではないでしょうか。
一足先に連休に入った私は,連休中,とりあえず英気を養って・・・
ということで,大学への数学の増刊号を買ってみました。
連休中,問題集を一冊仕上げてみようという算段です。
これと決めた1冊をきちんと仕上げるのが勉強では大事。
といいつつ,最近の私は,参考書や問題集を買っても,チラッと見て終わることが多いです。
特に,ネットで買った本だと,表紙だけ見て中身を見ていない本もあります。
「これではいかぬ・・・」と,GWで心を入れかえた次第です。
教育者として,子どもたちの模範とならないと,と心を入れかえたGW。
子どもたちの模範となるためには・・・
先日の天皇賞で,生まれて初めて買った馬券がたまたま当たって得たお金で問題集を買ったことは,秘密にしなければなりません。
運が良い(?)KEC高槻本校は,5月6日(土)より開校します。
5月無料体験も実施!
こんにちは。茨木本校2230です。
新受験生の皆さん,順調ですか?
新学期早々,ようわからん…てな感じでしょうか。
今度は自分の番,でもまだ実感伴わず,ですね。
こんなときは経験者に聞くのがいいです。
んっ?大丈夫なんとかなるって?
ご謙遜を真に受けてはいけません。
先日の高卒クラス開講式では,
「今ここにいる理由」として反省点をあげてもらいました。
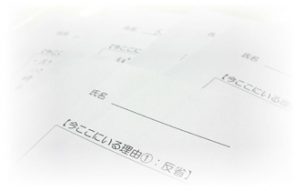
「勉強不足」(Tくん他多数)
「受験勉強そのものがわかっていない」(Oくん)
「定期テスト感覚で受けてた」(Hさん)
「真剣なスタートが遅かった」(Kくん)
受験勉強は質も量も確保しなければなりません。
基礎って何?その上で何を?
時期とレベルを見据えて進む必要があります。
「苦手科目の放置」(Aさん)
「丁寧さと雑さのアンバランス」(Nくん)
「テクニックに走り過ぎた」(Oさん)
「参考書に浮気」(Yくん)
正しい勉強の姿勢とは?合格点を取るための勉強バランスは?
堅実な知識って?案外わかっていないものです。
「詰めが甘かった」(Yさん)
「やってる気になっていた」(Kくん)
「生活習慣が悪かった」(Mくん)
雑さを指摘されてそれを改善することが大切です。
本質を理解して,ぶれない考え方ができるように。
しんどいけれど,己に厳しくなることも必要です。
彼らはきっと同じ過ちをしないよう努めることでしょう。
新受験生の皆さん,参考になさってください。
こんにちは。KEC高槻本校の数学・理科担当の川渕です。
国公立大学の前期入試が終わり,大阪府公立高校入試まであと10日となりました。
入試も大詰めになったこの時期,私も,下記の速読研修に参加しました。
リンク先は研修中の写真ですが,研修が始まる前はこんな感じでした。

大阪府公立高校入試の一般入試,英数国がA,B,Cの3段階になり,特にC問題対応がなかなか大変ですが,理科,社会も,地味に大変です。
2年前から,問題文の量,問題数,ともに大幅に増加しました。
資料から情報を素早く正確に読み取る力が,ますます問われています。
私の中3理科の授業でも,この時期になると,長文の問題を用意して演習を行っています。
ということで,早く読む力は国語だけにとどまらず,いろんな科目で必要になります。
大量の情報を素早く処理していく能力があれば,勉強にとどまらず,いろんなところで役立ちそうですね。
子ども達の能力を上げる取り組みの一環として,KECでは「速読」を導入しています。
体験も受け付けていますので,ご興味のある方は,ぜひ,KEC高槻本校までお問い合わせください。
ちなみに,入試で忙しいこの時期,なかなか処理能力が追い付かずブログの更新がままならない私も,速読の体験を検討しています。
KEC春期集中講座(新小4~新高3)新規生募集中!
詳しくはこちらのサイトをご覧ください。
こんにちは。茨木本校2230です。
立春もとうに過ぎたというのに,
寒い日が続いています。
みなさんは2230のマネして半袖でうろつかないように。。。
昨日は「大学入試説明会」。

高校と大学の違い。
試験の種類と必要な教科。
各科での取り組み方。
仕組みがわかれば,次は行動です。
「志望校判定模試」で現状確認,
「Reスタート講座」で学力充実,
「春の体験講座」で志望大別傾向チェックです。
重要度 大
↑
丨 ① ②
丨
丨
丨 ③ ④
丨
ーーーーーーーーーーー → 緊急度 大
上図は,重要度と緊急度の2次元マップです。
「入試」は重要だがまだ先なので①,
「期末テスト」は大切だしまもなく始まるので②,
「読書」は③,「ライン」は④に属しそうです。
限られた持ち時間。
いかに④を減らして①を増やすか。
「入試」がまだ①にあるうちに,
無理なく準備をすすめておきたいもの。
えっ,でもなかなかなぁ?
そんなアナタに,KECからのアドバイス。
「世界に向けてアンテナを張ろう!」
世の中には不思議なことや発見,またまた不条理など,
学校の行き帰りだけでは知り得ないことがたくさんあります。
興味あること,もっと知ってみたいこと,見つかるかも。
それらをよりよく学び研究できる場所が大学です。
どう,ワクワクしません?
だったら入試にも向かっていけますよね!
内から湧き上がる前向きな気持ちを大切に。
これがあれば大丈夫ですよ。
枚方本校の佐々木です。
絶対伸びない数学勉強法の動画がアップされました。
見ていただいたらわかると思いますが、少し補足しますね。
まず、タイプⅠの「数学の勉強をするときに問題を解く前から答えを広げている生徒くん」は、経験的に言うと文系の生徒くんに限定されます。
国公立大志望なので数学を避けて通るわけにはいかないけどできれば勉強したくない、そんな生徒くんです。
動画でも言いましたが、最初から答えを広げておかない習慣をつけましょう。
問題集を解くときに最初から答えを広げておく人は、解き方が頭にまったく入りません。
答えは閉じておくようにしましょう。
どうせ答えを見るので同じ事と思うかもしれませんが、全く違います。
次のような感じで取り組みましょう。
「わからない
→答えを見て理解する
→答えを閉じて解いてみる
→やっぱりわからない
→もう一度答えを見て理解する→続きを解く
→やっぱりわからない
→もう一度答えを見る
→続きを解く
(以下繰り返し)」
次に、タイプⅡの「数学の勉強をするときに答えをすぐ見てしまう生徒くん」についてです。
実は、この動画をアップしようと思ったのは、高3秋になって「答えを見たらわかるけど自分で気付けない生徒くん」がとても多いからです。
このタイプの生徒くんは、理系・文系どちらにもいます。
数学を暗記科目であるかのように解法暗記型の勉強をしています。
それでは、入試に必要な思考力は身につきませんよね。
1分ですぐに答えを見る人は最初から答えを広げている人とは違い、まじめに勉強すると頭には入ります。
でも高3の秋になると、特に模試を受けたあとに、こんな風に言います。
「先生、答えを見るとわかるんですが、自分で気づかないんです。どうしたらいいですか?」
数学の先生視点では、考える習慣が身についていないので、当たり前なんですね。
高3秋までくると改善する時間がありません。
今のうちに考える練習をしましょう。
模試も高2より高3春、高3春より高3秋の方が難しくなるので、高3秋になり数学の偏差値が下がって初めて気付く人もいます。
次回の動画はその改善策についてです。
魔法のような方法ではないですが、楽しみにしておいてください。
【過去の動画はこちらから】
・YOUTUBE動画チャンネルを開設しました!自己紹介
・第2回 志望校の決まっていない人への「受験生の心構え①」
・第3回 志望校が決まっている人への「受験生の心構え②」
・第4回 「学習習慣」