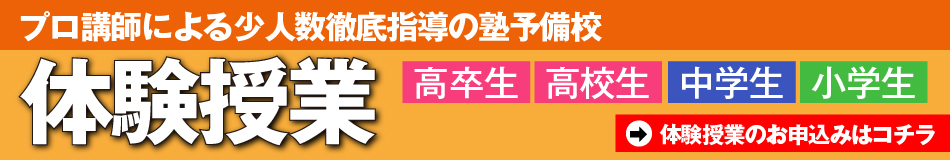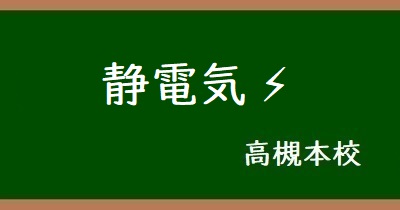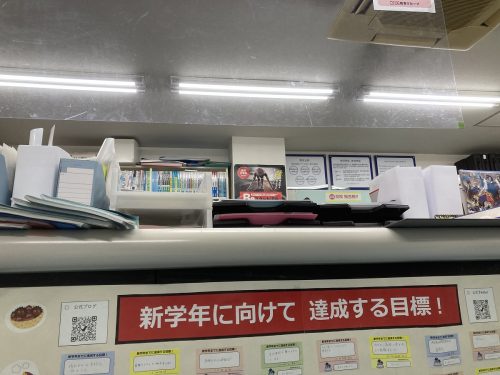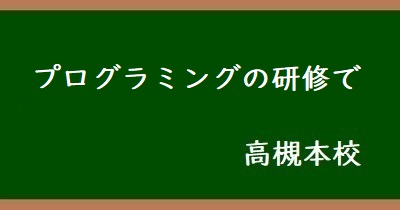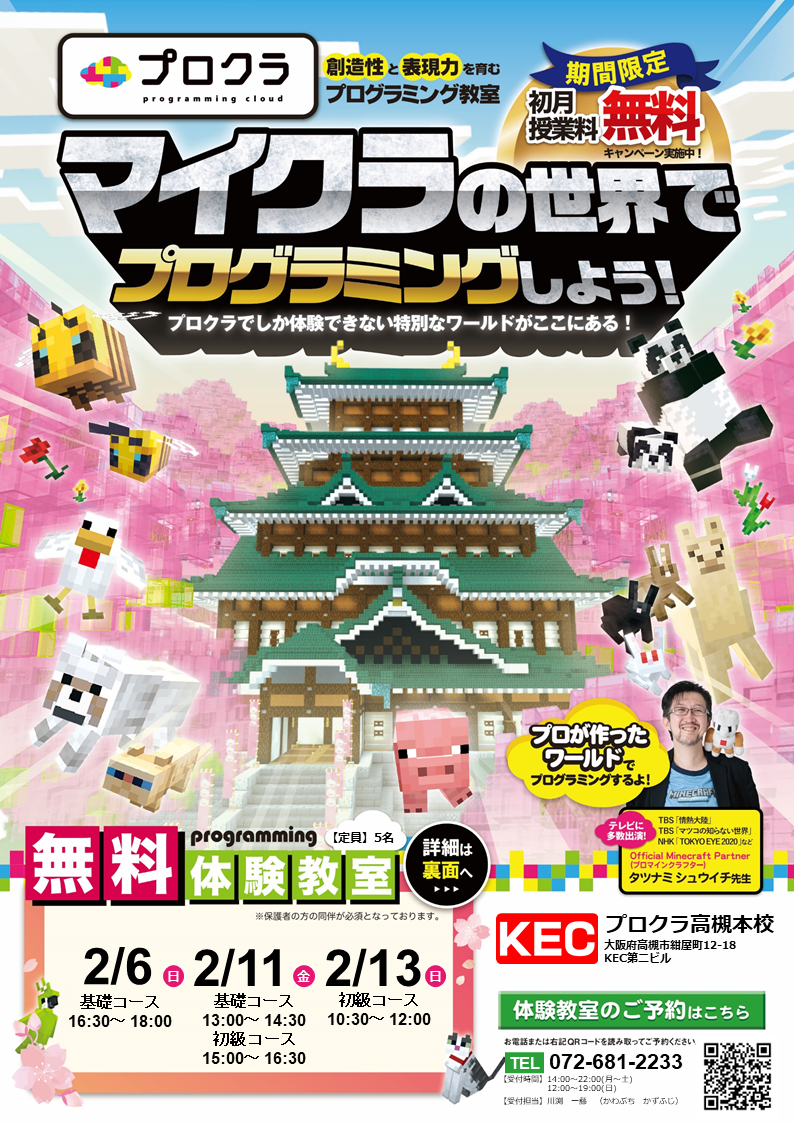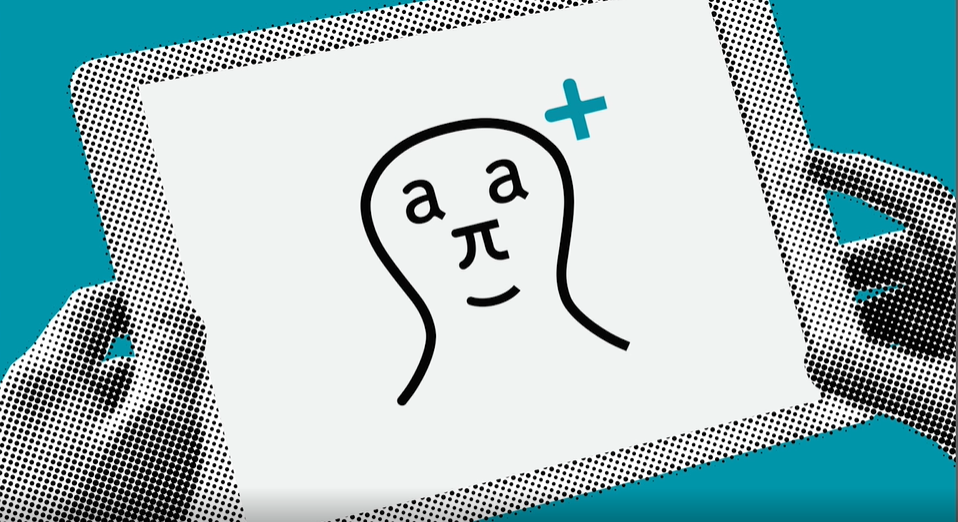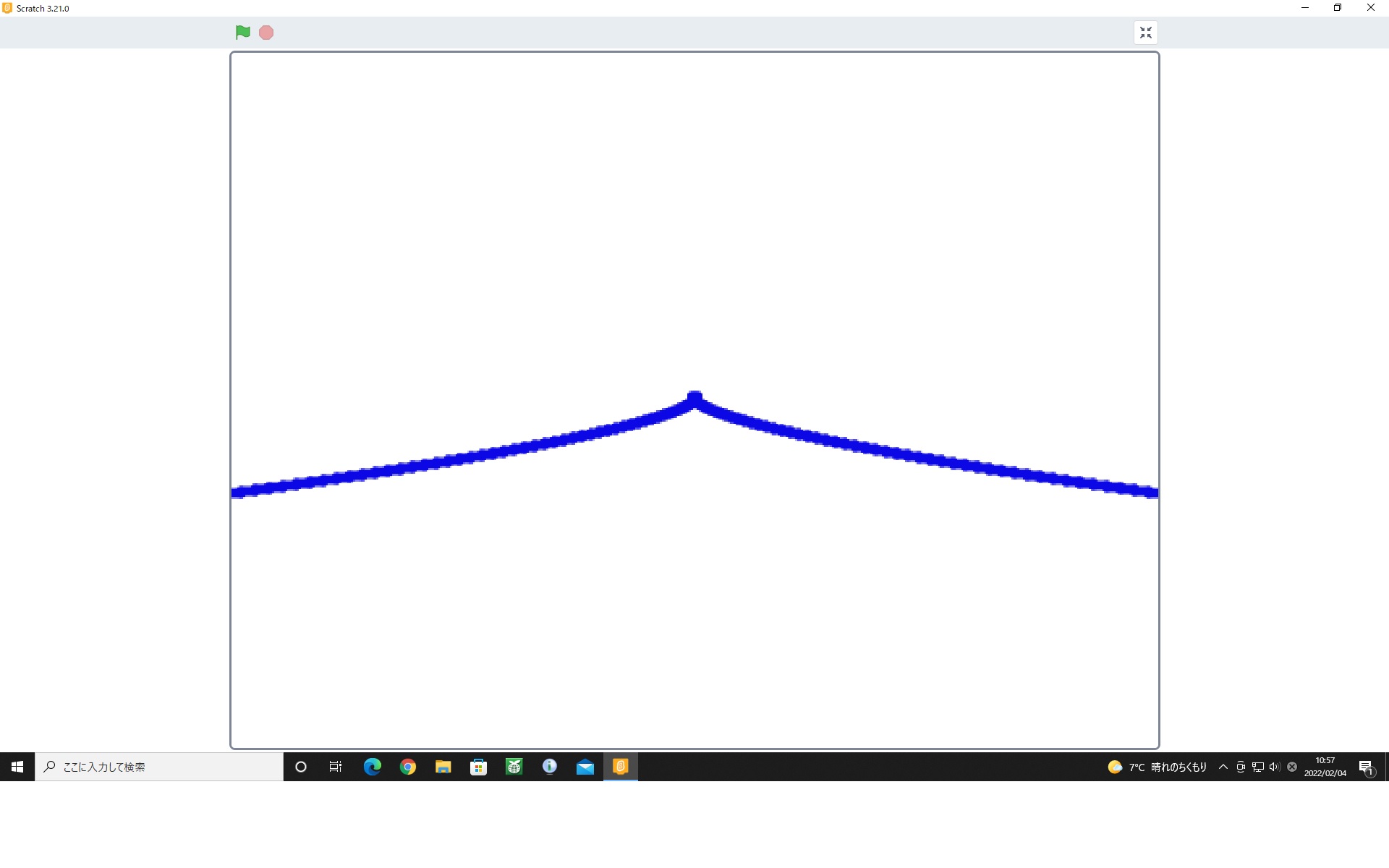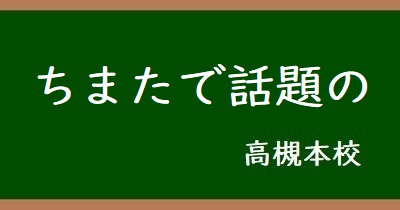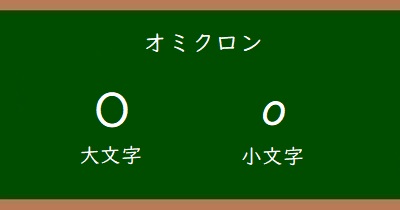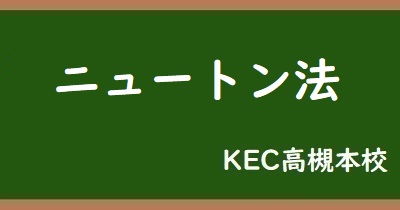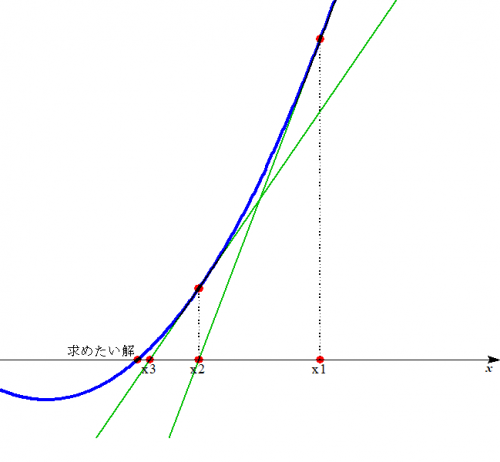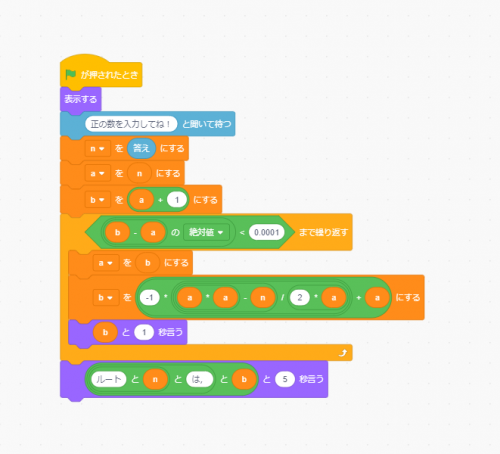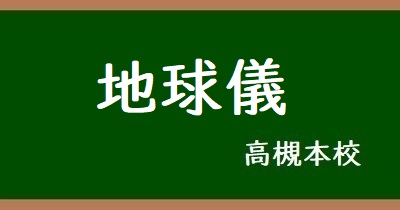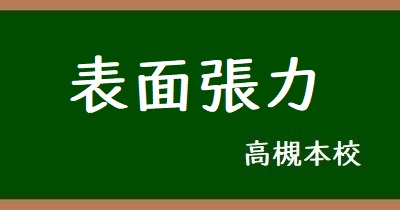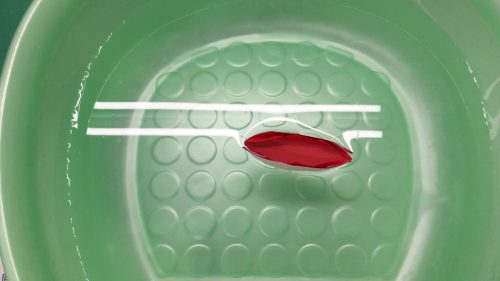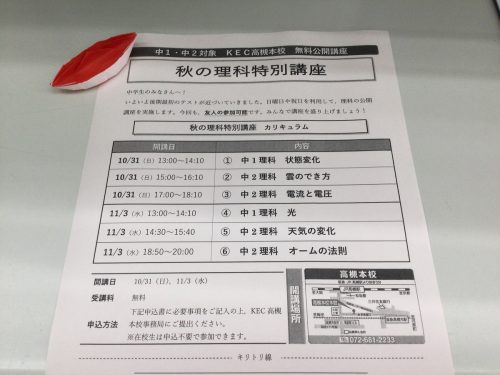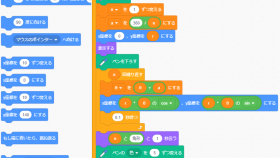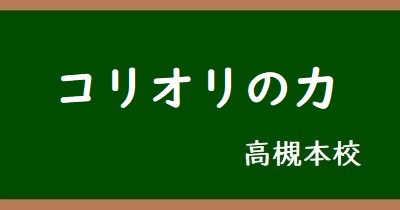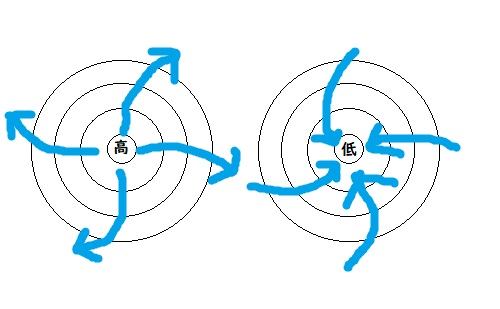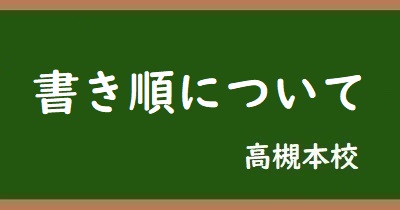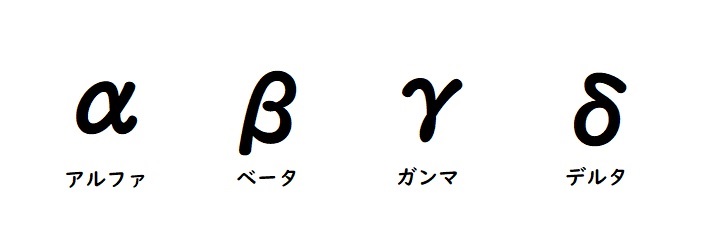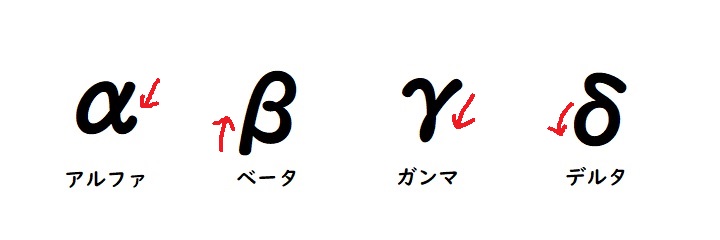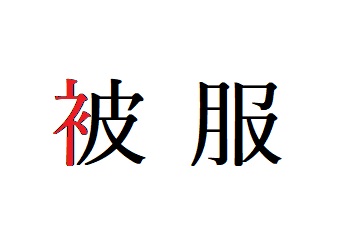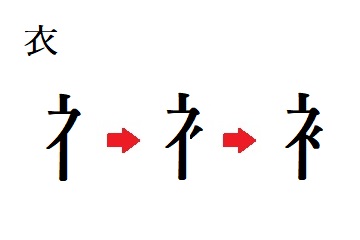こんにちは。KECの塾・予備校部門,高槻本校の数学・理科担当の川渕です。
先日,2月15日のこと。
アシスタントとこんな会話をしました。
「先生,奥様からチョコレートを貰ったんですか?」
「貰ったで」
「やっぱりハート形ですか?」
「いや,ふつうの形やで」
個人的には,あまりハート形が好きではありません。
食い意地が張っている私としては,ハート型のあのへこんだ部分が苦手です。
へこんだ部分があると,なんとなく損をした気分になるのです。
そんなハート形のことが気になったので,3月14日を前にして調べてみました。
調べてみると,ハート形を表す式があるそうです。
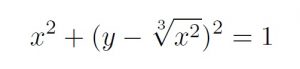
という式で,海外では「The Love Formula」と呼ばれているとのこと。
せっかくなので,恒例のスクラッチでコードを書いて描いてみました。
このハート形,面積について,面白い性質があります。
なんと,単位円と面積が同じです。
つまり,この式でできるハート形の面積は,半径1の円の面積と同じπになります。
ただ,ハート形の方が原点から遠い点を通過するので,例えば,四角形の箱に入れるとしたら,ハート形の方が大きい箱が必要になります。
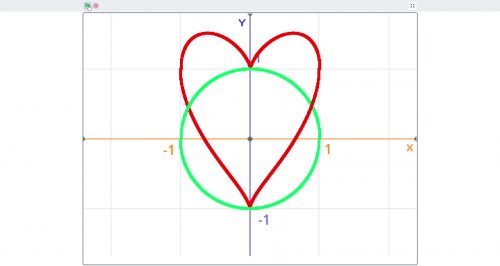
Scratch 3.21.0
【面積についての補足】
The Love Formulaの式をyについて解くと,ハート形の向かって右上(心臓でいうと左心房)の部分を表す式はy=x^(2/3)+√(1-x^2)…(1),右下(左心室)の部分はy=x^(2/3)-√(1-x^2)…(2)になります。
ハート形の右半分の面積を求めるためには上の式(1)から下の式(2)を引いてから積分しますが,この場合,(1)と(2)の差が2√(1-x^2)になります。
これは,円の面積を求めるときの式と同じなので,ハート形と円の面積は同じになることがわかります。
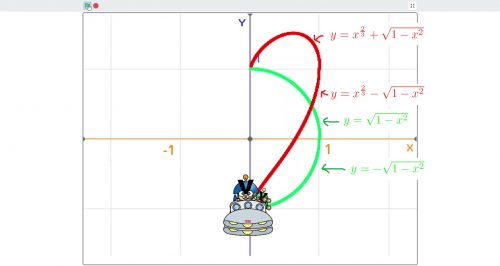
Scratch 3.21.0
ということで,ハート形はかさ張るわりには面積が大きくないことがわかりました。
ただ,本当にハート形のチョコレートを貰った時は,文句を言ってはいけません。
感謝の気持ちを忘れないことが,なにかと円満になる秘訣です。
■合格体験談・総集編はこちら
■KEC高槻本校公式サイトはこちら
■春期集中講座(小学生・中学生・高校生)受講生募集中!