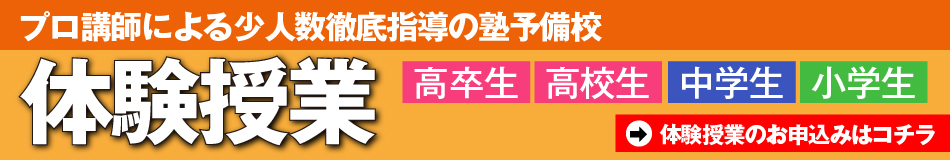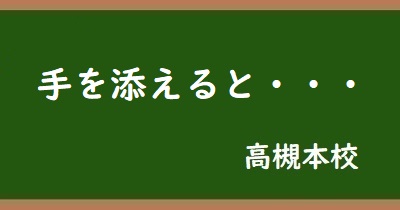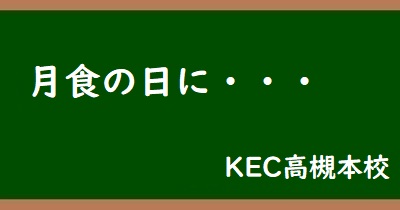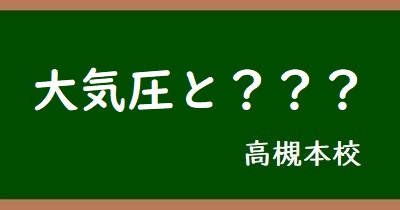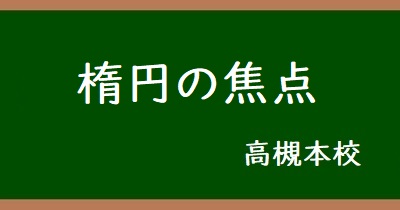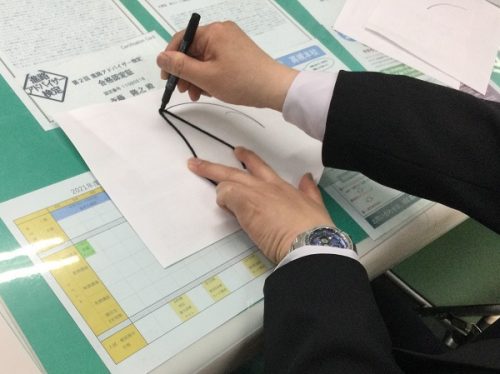こんにちは。KECの塾・予備校部門,高槻本校のお祭り担当の???です。
先日,動画をあげましたが,今回はその第2弾。
前回に引き続き,私のパワーをお見せします。
十円玉で空のビンにふたをします。
そのビンに私が手を添えると・・・
少しわかりにくいですが,お気づきになられましたでしょうか。
十円玉が,2回,動いています。
これは,私の念力で動いた・・・
のではなくて,ビンの中の空気が手で温められ膨張した結果,十円玉が動いたのでした。
「空気は温度が高くなると膨張する」ことを実感できる,定番の実験ですね。
※実験をするときは,「ビンを冷やし」「十円玉を水で濡らして」おくと良いです。
この実験,ある意味,われわれ塾講師の仕事を表しているかもしれません。
私たちがそっと手を添えることで,塾生の皆さんが成長し殻を破ることができる,そんな様子を表している気がします。
KEC生の皆さんが成長できるよう,わたくし???も日々努力しています。
そういえば,今回の動画,なにが大変って,無色透明なビンを手に入れるのに苦労しました。
コンビニでビンの飲料を買おうとしたのですが,あまり売られていないものですね。
特に,無色透明に限定するとなかなか難しい…
やむを得ず,自宅で愛飲しているウイスキーの空きビンを利用することにしました。
空きビンとはいえ,酒ビンを塾・予備校に持ち込むのはどうかと思ったのですが・・・
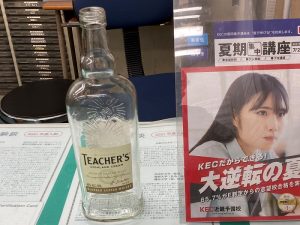
銘柄が「TEACHER’S」だからぎりぎりセーフかな,と拡大解釈しています。